—————————————————————
■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.367 ■□■
― ISOマネジメントシステムのテクノファ ―
― つなげるツボ動画版はじめました ―
*** SDGインパクト基準20 ***
—————————————————————
2015年に発表された国連「SDGsアジェンダ」についてお話をして
います。
SDGsとは、
“Sustainable Development Goals”の略で、「持続可能な開発」
と日本語訳されています。
今回は目標12についてです。
■■ 目標12 ■■
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する。
<12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費
と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の
下、すべての国々が対策を講じる。>
ここには「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)」
というものが出てきます。
ここで言う「持続可能」とは、人類が存続する限り(永続的)成り立
っていけるという意味ですから、消費と生産の関係性を永続的なもの
にする計画を作ろうという意味になります。
消費と生産の関係を永続的にしない、すなわち壊すものは何かという
と、最も影響を与えるものが「廃棄」です。消費には廃棄が付きもの
です。食べ物で言えばリンゴを食べてもその芯は廃棄されます(非可
食部廃棄)。衣服でも20年、30年着る人は少なく5年も経てば多く
の衣服は廃棄されるでしょう。住居もスクラップ&ビルドされて50
年も経つと街並みがかなり変わってしまいます。このような多くのも
の、温室効果ガスも含めて「廃棄問題」が目標12の最大の取組課題
です。
■■ 食料廃棄問題 ■■
その廃棄問題で強くフォーカスされているものが食料の廃棄問題です。
<2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの
食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーン
における食料の損失を減少させる。>
目標12には具体的に食料の廃棄を2030年までに半減させるとあり
ます。世界の食料廃棄の現状はどうなっているのでしょうか。
実は世界の食料廃棄の現状を調べようとしましたが、これがなかな
か把握しづらい問題であることが分かりました。Googleで検索し
てもズバリこれが食料廃棄量である、生産量に対する廃棄率である、
国別の廃棄率であるといった数字は出てきません。
農林水産省「平成 27 年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業
:海外における食品廃棄物等の発生状況 及び再生利用等実施状況
調査、平成 28 年 3 月 11 日 公益財団法人流通経済研究所」に
詳しいのですが、
(1)食品廃棄の定義、
(2)対象プロセス(生産、流通、小売り、消費)区分、
(3)非可食部、潜在可食部、可食部
などの線引きなどが各国バラバラでなかなか比較が難しいという
ことです。
■■ 世界の食料廃棄の現状 ■■
そうはいっても辛うじて以下のような情報は読み取ることが出来
ました。
米国では、2010 年における小売・消費者段階での食料損失は、
6,033 万トンと推計される。これは、小売・消費者段階での供
給量である 1.95 億トンの 31%を占めるそうです。
31%のうち、10%が小売段階での損失であり、21% が消費者
段階での損失であるとしています。データが古いのですが大き
くいって3分の1が廃棄されているということになります。
EUの情報もありました。
EU では、年 9,000 万トン、1 人 当たり年 180kg の食品が
廃棄されている(2006 年データ)との数値が紹介されていま
す。 また、ECのホームページ「Sustainable Food」では、食
品廃棄物の削減に取り組まなければ、「2020 年には食品廃棄
物が 1 億 2,600 万トンに増加する」と述べられている、と
の調査記載があります。
このように160ページの報告書にはいろいろなデータが紹介
されていますが、各国の状況を理解するのはなかなか困難で
す。しかし、EUの例のように一人当たりの年間の食品廃棄
量の比較資料がありますので、それを眺めてみるのがいいか
と思います(平成24年度推計)。
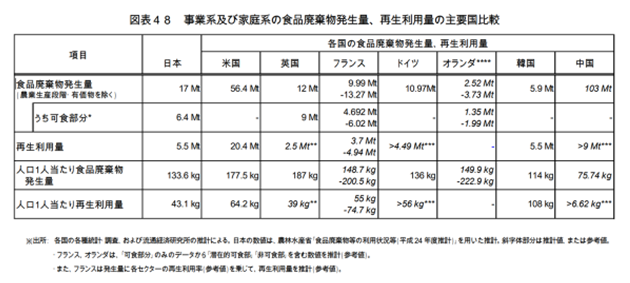
■■ 日本の食料廃棄の現状 ■■
各国の年間一人当たりの食品廃棄物発生量を整理しますと
次のようになります(平成24年)。
・日本 134Kg
・米国 178Kg
・英国 187Kg
・フランス 149Kg
・ドイツ 136Kg
・オランダ 150Kg
・韓国 114Kg
・中国 76Kg
別の資料には、日本には2017年度時点で約570万tの食品
ロス(可食部)があると報告されています。一時、日本は食
品ロス大国と表現されましたが、今では上記の表のごとく先
進国の中で際立っているわけではありません。一人あたり年
間134kg、毎日お茶碗3杯分のご飯を捨てているのと同じこ
と、と例えられています。



