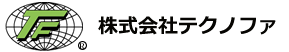044-246-0910
ISO審査員、キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。
1.はじめに
本書は、職場風土改善家・中村英泰氏の執筆によるもので、法政大学の田中研之輔教授が監修しています。中村氏は「職場を、個人がキャリア課題を解消し成長できる場にする」という信念のもと、これまでに700を超える職場風土の改善に携わってきました。
その過程で「今、職場で悩んでいることは何ですか」という質問をすると、最も多く挙がるのが「やる気・モチベーション」に関する悩みでした。上司からは「部下にやる気がない」、部下からは「上司が何を考えているかわからない」「この会社に将来性を感じられないので辞めたい」といった声が出てきます。悩みは深刻であるにもかかわらず、多くの場合は解決策を考えず、そのまま放置されているのが実情です。
上司は部下のことを、部下は上司や会社のことをよく知らないばかりか、知ろうともしない――こうした相互理解の欠如が背景にあります。多くのビジネスパーソンは会社や職場を「単に仕事をする場所」と捉え、「人生やキャリアを充実させる場所」とは考えていません。あるいは、働く中でそう考えられなくなってしまったのです。
また、たとえ相手が何を考えているかに関心を持たなくても、仕事の成果がある程度出ていればそれで十分だと考える人も少なくありません。その結果、デスクを挟んで向かい合う同僚との心理的距離は遠くなり、関係性が希薄になっています。
本書の目的は、この「職場における人間関係の改善」によって風土を変革することにあります。組織とは本来、「一人では成し遂げられない大きな目標を、強みや弱みを相互補完しながら協働することで、成果だけでなく互いのキャリア成長をも最大化するためのシステム」です。
実際に、いくつかの企業は社員同士の関係改善に取り組み、職場を「単なる職務を遂行する場所」から「職務を通じて互いの可能性を見出す場所」へと変革し、成果を上げています。
2.社員のやる気を奪う職場とは
やる気のある職場とない職場の違い
社員がやる気を失う瞬間は日常の中に数多く存在します。その瞬間が習慣となり積み重なると、我慢の限界を超えたときに「転職」という選択につながります。
では、どうすれば社員のやる気を高められるのでしょうか。ポイントは大きく2つあります。
- 物的側面:給与や賞与、役職、設備環境の改善、福利厚生や就業規則の整備など
- 人的側面:職場の雰囲気や価値観、社員同士の関係性、コミュニケーション、上司との関係、仕事のストレスや満足度など
特に人的側面は「やる気」に大きな影響を与えます。
職場風土が与える影響
これまで数多くの職場を見てきた中で、社員のやる気は「職場風土」に大きく左右されることがわかりました。職場風土には、社員同士の接触の量と接触の質の2要素が絡み合い、次の4つのタイプに分類できます。
| 接触の質\接触の量 | 少ない | 多い |
|---|---|---|
| 高い | 能動型風土 ・不満や問題が潜在している傾向 ・社員が人生の目的を意識しにくい |
創発型風土 ・社員同士の関係性が良好 ・イノベーションが生まれやすい |
| 低い | 離散型風土 ・社員が「自分は歯車」と感じやすい ・経営層が人を資源として扱う傾向 |
受動型風土 ・ルールや方針に忠実 ・短期成果に偏る |
各職場タイプの特徴
創発型風土
• 傾向:目標達成に向けて社員同士が協力し、相互調整を行う。キャリア成長を重視。
• 上司:社員同士の関係性を高める取り組みに力を注ぎ、成長と目標達成を両立させる。
• 状況:問題は発生しても、その都度関係性が強まり推進力となる。
能動型風土
• 傾向:目標や方針を全員で決定し、能動的に進める。
• 上司:1on1や評価面談で接触を増やし、社員の成長を支援。
• 状況:一見活発だが、やがて疲弊や内部対立が生じやすい。
受動型風土
• 傾向:方針は経営層が判断し、標準手順やマニュアルを重視。社員を「機能」として扱う。
• 上司:経営層の方針に忠実で、社員のキャリア充実は重視しない。
• 状況:離職があっても「合わなかった」と処理し、学びにつながりにくい。
離散型風土
• 傾向:経営層が経験則で方針を決定。社員を「交換可能な歯車」と見なす傾向。
• 上司:新しい取り組みに消極的で、社員の成長を重要視しない。
• 状況:社員同士の関係性が希薄。「親睦会は経費での飲み会にすぎない」といった声も聞かれる。
職場風土を改善するには
社員のやる気を奪う要因は職場タイプによって異なりますが、共通して言えるのは社員同士の関係性の改善がカギであるという点です。職場風土は、長年の関係性の積み重ねから形成される「文化」のようなものです。
関係性を改善する際には、組織行動学のソーシャル・キャピタルの考え方が有効です。これは「人と人とがつながり合うことで得られる資源」であり、組織の生産性や目標達成を促すとともに、社員が人生の使命を果たし社会に貢献する力ともなります。
ウェイン・ベーカーの著作にもあるように、ソーシャル・キャピタルは職場に「創発」を生み出す重要な要素なのです。
3.職場風土の改善は「関係密度」がカギ
関係密度を高める5つのポイント
「関係密度」を高めるために重要なのは、接触の量と質です。
接触の量が増えるほど相手に好印象を持つようになる心理現象を「ザイオンス効果」といいます。これは社員同士の関係づくりにも当てはまります。
人間関係を築く上で、接触は「他人」から「同士」になるために欠かせないものであり、接触の量がゼロでは関係性を育むことはできません。
しかし一方で、ただやみくもに話しかければよいというものでもありません。
接触の質が重要です。本人が良かれと思っていても、質の低い接触を重ねるだけでは「関係密度」は高まりません。
質の高い接触を意識するために、次の5つのポイントを心に留めておくことが大切です。
- 社内にいる人を「他人」でも「社員」でもなく、同士として認める。
- 社内の人と、データではなく目的を共有する。
- 社内の人とは、メールではなく対話で関わる。
- 社内の人から、「私も一員」と認めてもらう。
- 社内の人と、雑談ではなくビジョンを語り合う。
「関係密度」の向上を阻害する「心理的な溝」
「関係密度」を高めるために取り組む際、注意すべき点が2つあります。
それは、社員同士の距離を縮めることと、その距離の拡大によって生じる心理的な溝を埋めることです。
まず、職場において縮めるべき「距離」には、次の3つがあります。
- 役職や階層の距離
- 部署間の距離
- 個人の心理的な距離
これらの距離が開くことで、知らないうちに「心理的な溝」が生まれていきます。以下では、その具体例を見ていきます。
① 役職や階層の距離で生じる溝
この溝は、たとえば「社長はこう考えているはずだ」「部長がこう言ったのだから」といった忖度によって生まれます。相手に直接真意を確かめれば距離は縮まるのですが、「相手は偉い人だから」との思い込みから、実際の対話が行われず、憶測や推測、意見の食い違いが生じてしまうのです。
② 部署間の距離で生じる溝
部署間の溝は、企業内でしばしば見られます。
たとえば、企画や製造部門からは「営業は何も考えていない」との声が聞かれ、営業部門からは「もっと売れるものを作ってほしい」といった不満が出ることがあります。
本来、業務効率化や専門性向上のために構築されたシステムや分業体制が、結果として部門間の関係を分断し、職場の関係密度を下げる要因になってしまっているのです。
③ 個人の心理的距離で生じる溝
「会社の隣の席の人が何をしているのかわからない」といったケースも珍しくありません。
以下のような理由から、心理的な距離が生まれてしまいます。
- いつも忙しそうで話しかけづらい
- 話しかけたら難しいことを言われそうで面倒
- 話しかけなくても業務上は困らない
このような小さな壁が積み重なり、職位や役職に関係なく「個人間の心理的な溝」ができてしまいます。
社員同士が縮めなければならない3つの距離
職場における「距離」には、次の3つの種類があります。
① サイロ(Silo)=役職や階層の距離
「サイロ」とは、本来は農場にある円筒型の穀物倉庫を指します。上から穀物を入れると、下から流れ出る構造になっており、上から下への一方通行を象徴しています。
組織においても同様に、縦割りの力が強く働くことで、上司と部下の間に分断が生じ、コミュニケーションが滞る状況を表しています。
② スラブ(Slab)=部署間の距離
「スラブ」とは「石板」や「平板」を意味します。
会社全体で集まる場があっても、部署ごとや事業所ごとに人が固まってしまう光景は珍しくありません。
このように、物理的な距離や組織の壁が関係性を途絶させてしまう現象を「スラブ化」と呼びます。
③ バウンダリー(Boundary)=個人の心理的距離
「バウンダリー」とは「境界」を意味します。
学歴、年齢、職位、所属部署、勤務地など、さまざまな要因から、相手との関係づくりをためらってしまうことがあります。
このようにして生まれる心理的な「壁」が、人と人との関係密度を下げる要因となるのです。
「関係密度」を高めると、多くの「強み」が手に入る
「関係密度」が高い職場の社員には、次のような共通点が見られます。
- 企業や社長、そして他の社員の考えと、自分の考えに共通点があると感じている。
- 社員同士が、相手の部門や役職といった所属をあまり気にしていない。
- 「なぜこの企業で働くのか」「なぜこの仕事をしているのか」「自分は何を実現したいのか」といったテーマを話し合う機会が多い。
- 会議などの場で、自分の発言が「正しいか・間違っているか」といった評価を気にする必要がない。
- 働き続けることで、自分の考えや価値観がより明確になっていくと感じている。
これらの特徴は、次の2つの調査・実践結果をもとに整理されたものです。
- 企業業績が良く、社員の離職率が低い企業において、外部面談を通じて「関係密度の高さ」が確認された社員の声。
- 職場風土改善プロジェクトに関わった企業のメンバーへのヒアリングで得られた意見。
「関係密度」の低い職場が抱える大きな問題
「関係密度」の低い職場で働く社員に共通して見られる特徴として、次のような点が挙げられます。
- 企業や社長、他の社員の考え方に対して違和感を覚える。
- 社員同士の交流が、部門や役職といった「所属」に基づいて形式的に行われる。
- 「なぜこの企業で働くのか」「なぜこの仕事をしているのか」「自分は何をしたいのか」といった問いを考えるのが苦痛である。
- 会議などで不用意に発言すると余分な仕事が増えるため、発言を避ける傾向がある。
- 働き続ける意欲が低く、自分自身に対しても期待を持てない。
一方で、近年の社会人に「企業を選ぶ基準」を尋ねると、「何をするかよりも、誰と働くか」を重視するという声が多く聞かれるようになっています。
つまり、職場内の「関係密度」が個人のモチベーションや成長意欲に大きく影響していると言えます。
出典:
中村 英泰 (著)、田中 研之輔 (監修)(2022)「社員がやる気をなくす瞬間 間違いだらけの職場づくり」アスコム
吉末直樹(つづく)