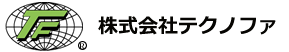044-246-0910
ISO 14064は、温室効果ガス排出量のモニタリング(算定)、報告、検証等についてのISO規格です。2002年からISO/TC 207において規格づくりが開始され、2006年3月に発行されました。
ISO 14064に関連する規格として、ISO 14065と14066があります。ISO 14065は検証機関等の認定のための要求事項が書かれた規格で2007年4月に発行されました。ISO 14066は検証チームの力量についての要求事項が書かれた規格で2011年4月に発行されました。
ISO 14064は、次の3部から構成されています。
|
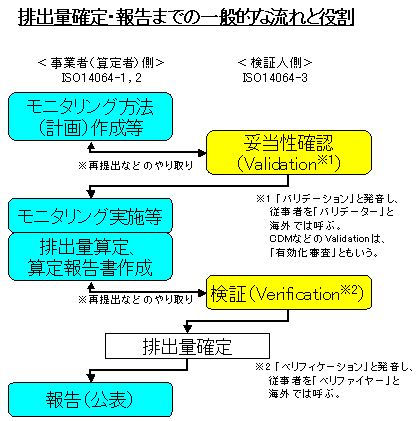 簡単に言えば、温室効果ガスを排出する事業を行っている組織が算定を行い、それとは別の人が検証人として算定結果が正しいか検証します。検証は多くの場合検証機関が行います。
簡単に言えば、温室効果ガスを排出する事業を行っている組織が算定を行い、それとは別の人が検証人として算定結果が正しいか検証します。検証は多くの場合検証機関が行います。
ISO 14064の第1部はインベントリ型(キャップ&トレード型)での算定について、第2部はプロジェクト型(ベースライン&クレジット型)での算定について、第3部は妥当性確認・検証について記載されています。第1部と第2部は算定者の行うこと、第3部は検証人の行うことが記載されているとも言えます。
ちなみに、規格の中に出てくる用語の
“directed action”と”greenhouse gas project”の違いは、第1部と第2部の違い、つまりキャップ&トレード型とベースライン&クレジット型の違いを理解しなければ、表面的にしか理解できません。本当の意味で理解したと言う為には、広範で深い学習が必要です。テクノファのセミナー「ISO 14064-1温室効果ガス排出量算定コース」(コースID:EK78)をご受講の際はこれだけでも理解してお帰りいただきたいと思います。