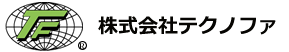044-246-0910
ISO審査員、キャリアコンサルタントの皆さんに有用な情報をお届けします。
1.はじめに
『新しいキャリアの見つけ方』は、有山徹氏が自身の経験をもとに執筆した一冊です。氏は40歳になるまでに5度の転職を経験し、その過程で「プロティアン・キャリア」という考え方と出会ったことが、大きな転機となりました。現在はプロティアン・キャリア協会の代表理事として、キャリア開発の実践支援に取り組まれています。
プロティアン・キャリアとは、これまでの経歴をすべて肯定しつつ、未来を見据えて前進しようとする姿勢に基づいたキャリア論です。変化を前提とした未来志向の考え方であり、自分自身がより幸せに、より良く生きることを目指すと同時に、周囲の人々にもポジティブな影響を与えることを重視しています。
本書には、キャリア・コンサルタントにとって学びの多い内容が詰め込まれており、キャリア開発を考える上で非常に有益な一冊といえるでしょう。
2.予測不能な時代のキャリア形成とは
1)キャリアの主導権は自分で握る
現代はVUCA(*1)の時代といわれています。かつてのように終身雇用を前提とした画一的なキャリアは姿を消し、明確な「ロールモデル」が存在しないことから、多くの人が「モデルロス症候群」に陥っているといわれます。終身雇用時代には会社がキャリアを用意してくれましたが、今は自分自身でキャリアの主導権を握らなければならないのです。
*1 VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語。社会やビジネスにおいて未来の予測が難しい状況を指す。
2)やりたい事のない人へ
「あなたのやりたいことは何ですか」と問われて、即答できる人は多くないでしょう。けれども「誰かのためにやりたいこと」を考えると、「両親のために家を建てたい」「地域社会に貢献したい」といった思いが自然に浮かぶ場合があります。そうした「やりたいこと」や「大切にしたいこと」を見つけることから、新しいキャリアは始まるのです。
3)人生の成功を決めるのはあなた自身
プロティアン・キャリアの考え方では、目標そのものよりも、それに向かうプロセスが大切だとされています。キャリアプランは決して完成するものではなく、常にアップデートされる「永遠のベータ版」と捉えられます。重要なのは、変化を前提にその時々の「やりたいこと」を言葉や文章で明確化し、実際に行動を起こすことです。
これまでの社会では、経済的豊かさや地位といった「外的基準」によって成功が測られてきました。しかし、プロティアン・キャリアの視点では、自分の価値観に基づいて幸福感を得られる状態や、夢に向かって努力する過程で成長を実感できることこそが、本当の成功と考えられます。
4)キャリアは「過去」、「現在」「未来」をつなぐもの
また、「成功を自分で決める」という視点を持つことで、これまで歩んできた道の意味付けが変わってくるかもしれません。一本道のキャリアであれば寄り道はマイナスと捉えられるかもしれませんが、遠回りや経験の積み重ねが結果的に新たな道を開いた可能性もあるのです。
大切なのは「過去」ではなく、「これからどうキャリアを築くか」です。そのためには、自分自身の軸を持ち、未来を見据えて戦略を立てる必要があります。そして、具体的な行動に落とし込み、自ら変化を生み出していくことが重要になります。
3.未来を創るプロティアン・キャリア戦略
多くの人は「キャリアとは過去に築かれたもので、今さら変えることはできない」と考えがちです。しかし、これは大きな誤解です。キャリアとは、よりよく生きるためにどうすればよいかを考えることであり、どんな人でも、いつからでも、何歳からでも創り直すことができるのです。
かつてのキャリアは、大企業への入社や管理職としての経験、あるいは起業といった「経歴の実績」が重視されていました。しかし現代においてキャリアとは、履歴書や職務経歴書に記される文字情報に限らず、これまでの経験と、これからの生き方のプロセス全体を指すものへと広がっています。
「このままでいいのだろうか」と将来を不安に思うとき、すでに目は未来を見ています。過去にとらわれるのではなく、未来を構想することこそがキャリアづくりの第一歩です。
1)キャリア・プラトーとキャリア・オーナーシップ
若いころはがむしゃらに働くことで成長を実感できますが、経験を積むにつれ自己成長を感じにくくなり、「昇進の可能性」や「のびしろ」にも限りが見えてきます。この「頭打ち感」をキャリア・プラトーと呼びます。その原因は個人の能力不足ではなく、キャリアが会社によって握られてしまっていることにあります。
本来キャリアは個人が主体的に考え、動かしていくものです。その姿勢をキャリア・オーナーシップといい、自らキャリアの舵を取ることが求められます。
2)組織との関係性
多くの人は組織に属して働いています。その中で自立したキャリアを築くには、組織に貢献し信頼を得ることが欠かせません。つまり、組織のミッションと自分のやりたいことの重なりを見出し、依存関係ではなく相互にプラスとなるパートナー関係を築くことが大切です。
3)プロティアン・キャリアの3つの特徴
- 未来志向
これから送る人生に目を向ける。過去のキャリアも未来に向けて新たな意味を与えることができる。 - 変幻自在
キャリアは一本道でなくてよい。いつでも、どんな状況からでも新たに築き直せる。 - 心理的成功
自分が幸福だと思える状態を定め、その実現に向かうプロセス自体にも幸せを見出す。組織とのミッションを重ね合わせながら、自らの手に取り戻したキャリアで「心理的成功」を目指す。
4.自分のタイプ・価値観を確かめる方法
「やりたいことが何かわからない」という人は少なくありません。原因の多くは、考え始める「起点」が見つからないことにあります。そこでまずは次の2つの視点から考えてみましょう。
① 誰に、何をしてあげたいか?
「上司の役に立ちたい」「リーダーシップを発揮してチームをまとめたい」「子どもを幸せにしたい」など、対象を設定することでやりたいことの輪郭が見えやすくなります。
② やりたくないことは何か?
「満員電車に乗りたくない」「一日中デスクに座っていたくない」など、避けたいことを明確にすることも出発点になります。 これにより、自分に合った働き方の方向性が浮かび上がります。
1)ライフラインチャートで価値観を探る
次に、自分の価値観を深掘りする方法としてライフラインチャートを作成します。
- これまでの人生を振り返り、どのような環境で育ち、どんなことに興味を持ってきたか
- 所属してきたコミュニティでどんな役割を担ってきたか
- どんなときに幸福感を覚え、逆に不幸を感じたか
これらを時系列に書き出すことで、自分の幸せの基準や大切にしている価値観が明確になります。
2)「自分を知る」×「他者に知ってもらう」
自己理解には、2つの側面があります。
- 自分の知っている自己
自分の得意なことや苦手なことを正しく把握し、変化する環境にどう対応できるかを理解する。 - 他人が知っている自己
自分では気づいていないけれど、他人から見て強みだと思われている部分。これを広げることで、周囲から新しいチャンスがもたらされやすくなります。
プロティアン・キャリアでは、「自分も他人も知っている自己」を拡げることを目指します。これにより、自分の強みを発揮できる機会が増え、より柔軟に未来を切り開いていくことが可能になります。
5.自分の武器・価値をみえる化する「キャリア資本」
「自分の強みを生かして働こう」とよく言われますが、他人より圧倒的に優れた強みを持つ人は多くありません。実際には、強みは絶対的なものではなく、「どの場面で発揮されるか」「誰と比較されるか」 によって変わる相対的なものです。つまり、強みは他者との関係性に生まれる「ポジショニング」だといえます。
企業が持つ資本をどう活用・投資していくかで経営戦略が決まるように、個人もまた「自分が持つ資本」を見える化し、戦略的に活かすことが求められます。
1)プロティアン・キャリアにおける「3つの資本」
プロティアン・キャリアでは、自分を企業に見立てて以下の3つの資本を整理します。
- ビジネス資本(知識・経験)
- 専門スキルや業界経験など、これまでの仕事で培った知識やノウハウ。
- ただし、専門知識は環境変化によって時代遅れになるリスクもあるため、どの職種でも活かせる 「ポータブル・スキル」(課題発見・計画立案・実行力など)がより重要となります。
- 社会関係資本(人的ネットワーク)
- キャリアを飛躍させる大きな力は「人とのつながり」です。
- 大きく2種類に分けられます。
- 結束型ネットワーク:家族や友人など、価値観を共有する安心のコミュニティ。
- 橋渡し型ネットワーク:趣味や異業種の仲間など、異なる世界との緩やかなつながり。新しい機会を生みだします。
- 経済資本(貯金・資産)
- 新しい挑戦を始める際には、初期投資や学び直しにコストが必要となります。
- 心理的成功を目指すにしても、資金の裏付けがあることで選択肢が広がり、挑戦の自由度も高まります。
2)「キャリア資本」の見える化
これら3つの資本を棚卸しすることで、
- 自分がどの資本を強みにできるのか
- どの資本をこれから補強するべきか
しなければならない事が明確になります。
言い換えると、「自分のキャリアを経営する」ための財務諸表をつくるようなものです。資本の分配と投資戦略を考えることで、未来志向のキャリアづくりがぐっと現実的になります。
参考文献:
有山 徹 (著), 田中 研之輔 (監修)(2022)「今のまま働き続けていいのか 一度でも悩んだことがある人のための新しいキャリアの見つけ方 自律の時代を生きるプロティアン・キャリア戦略」アスコム
吉末直樹(つづく)