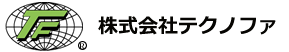044-246-0910
ISO審査員、キャリアコンサルタントの方への有用な情報をお伝えします。
1.はじめに
本書の著者である法政大学田中研之輔教授は、大学での教育活動に加え、キャリア開発に取り組む企業においても、一人ひとりのキャリアに関する悩みに寄り添い、働くことを前向きに捉えられるよう、持続的な変化と行動を支援されています。その実践を通じて、多様な人々との出会いと経験を積み重ねてこられました。
私たちは、長く働くなかで必ずキャリアについて悩む局面に直面します。そのとき、きっかけをつかみ自ら一歩を踏み出さなければ、悩みの悪循環から抜け出すことはできません。
悩み続ける状態から「キャリアを主体的に考える状態」へ移行するためには、繰り返しの実践を通じて行動を習慣化していくことが欠かせません。しかし、多くの人はその習慣化に至る前に立ち止まってしまいます。そうした状況を打開するために提唱されているのが、本書で扱う「キャリアオーナーシップ」です。
キャリアオーナーシップとは、組織に自分のキャリアを委ねるのではなく、自らがキャリアの主体者=オーナーとして日々の意思決定と行動を積み重ねていく考え方です。
本書では、次の二つのゴールを目指しています。
- やりがいを感じながら、自分の可能性を最大限に発揮すること
- 個人と組織の最善の関係を築き、自分らしく働きながら組織の成長にも貢献すること
2.今なぜ、キャリアオーナーシップなのか
1)誰でもキャリアのオーナーになれる
そもそもキャリアとは何でしょうか。キャリアとは、仕事や職業を通じて歩んできた人生の軌跡、そしてこれから進む方向性を指します。そこには単なる職歴や経歴だけでなく、個人の価値観や関心、能力や人間関係なども含まれます。
本書では、キャリアを「これまで取り組んできたこと(過去の実績や現在の状況)」と「これから生涯を通じて取り組むこと(未来の行動)」の総体と定義します。
しかし、いま主体的にキャリアオーナーシップを持って働いている人は決して多くありません。その結果、以下のような傾向が見られます。
- 働くことへの心理的幸福感が低い
- 企業へのエンゲージメントが低い
- 生産性や競争力が低い
- 環境の変化に対応できず、スキルアップが進まない
2)働き方の歴史的転換
新型コロナ対応を契機に、多くの企業が在宅勤務を導入しました。現在ではオフィス勤務とのハイブリッドワークが定着しつつあります。
在宅勤務が広がる中で、評価の軸は「プロセス」から「成果」へと移行しました。年功序列や終身雇用の制度疲労が明らかとなり、パフォーマンス次第で年齢を問わず雇用が継続される一方、成果を出せなければ退職勧告を受けるケースも増えています。
いま私たちが目の当たりにしているのは、日本型雇用の歴史的転換です。
- 終身雇用制度の見直し
- 成果主義の導入
- 副業・兼業の推進
- メンバーシップ型からジョブ型への移行
など、人事制度改革が加速しています。
3)キャリアの自律
キャリアオーナーシップを持続する上で欠かせないのが「キャリアの自律」です。これは、個人と組織、同僚、社会など多様な関係性をより良いものに構築し、相互の成長を促す行動を指します。
今必要なのは、従来の「組織に委ねられたキャリア」から「自律的なキャリア」への移行です。その実践的な手法を示しているのが、最新の知見である「プロティアン・キャリア」です。
4)人への投資の本質
これからのキャリア形成では、「人への投資」が不可欠です。その中核となるのがキャリア資本の蓄積です。キャリア資本は次の三つから成り立ちます。
- ビジネス資本:知識・スキルなど仕事を通じて得られる資源
- 社会関係資本:会社内外や地域、趣味などを通じた人的ネットワーク
- 経済資本:金銭や資産、不動産などの経済的資源
環境の変化に翻弄されるのではなく、自ら適応し、さらには働き方そのものを主体的に変えていくことが求められます。アダプタビリティ(変化対応力)とアイデンティティ(自分らしさ)を軸に据えることで、歴史的転換期においても自らのキャリアを切り拓くことができます。
キャリアオーナーシップ実現の3つの視点
キャリアオーナーシップを実現するには、次の三つの取り組みが重要です。
- 1.個人からのキャリアオーナーシップ:自らキャリア形成を重視し、日々の行動を通じて成長を追求する。
- 2.組織からのキャリアオーナーシップ:社員のキャリア形成を支援する人事施策や研修、制度を提供する。
- 3.個人と組織の関係性の改善:相互に成長を促す良好な関係を持続的に構築する。
3. キャリアオーナーシップを持続させる思考と行動
キャリアオーナーシップを実現するための20の行動指針を以下説明します。
1)軸を起点に「ありたい自分の生き方」を構想する ― 個人パーパスの策定(行動指針その1)
キャリア形成を考える際、支柱となる軸は大きく3つあります。
- 仕事軸:会社の業務を中心にすべてを選択していく考え方。かつての主流ですが、今はワークとライフのバランスや多様性の尊重が求められる時代です。
- 他人軸:他者の評価や状況に左右される考え方。例えば、同期の出世を素直に喜べないなど、ネガティブに働く場合があります。
- 自分軸:自らの価値観や意思を基盤に選択していく考え方。キャリアオーナーシップを考えるうえで、もっとも大切にすべき軸です。
特に重視したいのは「自分軸」です。やりたいことを基点にキャリアを考え、自ら行動していく姿勢を持つことが重要になります。
その第一歩が「個人パーパスの設計」です。
個人パーパスとは、仕事や人生を通じて自分が大切にしたい価値観や揺らぐことのない存在意義を明確にすることです。過去にとらわれるのではなく、未来に向けてどんなキャリアを創造していきたいかをイメージし、言語化していきましょう。
ワークの例としては:
- 1年後、どんな自分でありたいかを考え、個人パーパスを描いてみる。
- 3年後を見据え、自己投資の戦略を設計する。
- 人生全体を通じて「どう生きたいか」を問い直す。
パーパスを策定するポイント
- 1.キャリア形成のステージに応じてアップデートする
- 2.1つに限定せず、複数あってもよい
- 3.自分のポテンシャルを伸ばす羅針盤として活用する
2)自己を理解し、仕事を通じて自己実現・表現する ― 4L理論でセルフチェック(行動指針その2)
自己理解を深めるためには、現在のキャリア状態を客観的にチェックすることが大切です。その方法のひとつが「4L理論」です。
4L理論では、人生を以下の4つの領域で捉え、バランスを保つことが意味のある人生につながるとしています。
- 仕事(Labor)
- 学習(Learning)
- 余暇(Leisure)
- 愛情/思いやり(Love)
これらを定期的に振り返り、自己評価することをおすすめします。特に「仕事」と「学習」が4点以上であれば心配はありません。注目すべきは「余暇」の充実度です。
余暇の充実が鍵となる理由
余暇を楽しんでいる人は、主体的に活動している傾向があります。その理由としては:
- 自らの変化や成長を実感できる
- 目標を設定し、達成に向けて取り組める
- 仲間と一緒に活動できる
- 目の前のことに没入できる
- 継続的な取り組みによって心身のリフレッシュができる
これらはすべて、仕事にも応用可能です。つまり 「余暇での主体的・没入的な行動を、仕事にも取り入れる」 ことが、特にミドル・シニア層のキャリア活性化につながるのです。
学習・愛情(思いやり)にも広げる
学習においても、継続的に学びを続けられている社員は高いモチベーションを保っています。そのエネルギーや習慣を、ビジネスシーンにも活かすことができます。愛情(思いやり)の領域も同様に、日常の関係性から得られる主体性や共感を、仕事に結びつけることが可能です。
3)心の内側にある好奇心やモチベーションを起点にする ― 幸福度の高い働き方の実現(行動指針その3)
国連が毎年発表している「世界幸福度調査」によれば、2025年の日本の順位は55位でした。この結果は、私たちが働き方やキャリアのあり方を見直す大きなきっかけになります。
幸福度を高めるための核心は、組織依存型キャリアから自律的キャリアへのシフトです。
「働くこと」は、単なる生活の糧を得る手段ではなく、
- やりがいを感じ、
- 目の前の仕事に没頭し、
- 自分の可能性を伸ばしていく営み
であるべきです。
その目的は、現状の不満や課題を解決するだけでなく、よりよい未来や社会を創造することにあります。一人ひとりが自らの好奇心やモチベーションを起点に、「自分にできることは何か」を考え、行動を起こすことが求められています。
4)新しいものを受容し、自己変革を積み重ねる ― リスキリング(行動指針その4)
近年注目されている「リスキリング」や、副業・兼業の推進は、組織だけでなく個人にとっても大きな機会です。ここで大切なのは、「自分への投資」もまた「人への投資」と同じくらい重要であるという認識です。
リスキリングとは
社会の変化に応じて新しい知識を学び、新しいスキルを身につけることで、これまでとは異なる業務や職業にも対応できる力を養うことを意味します。
リスキリングが求められる3つの理由
- 1.テクノロジーの進化
HRテクノロジーを含む新しい技術を活用するためには、最新の知見やスキル習得が不可欠です。 - 2.キャリアの自律化
組織任せではなく、自ら新しい業務や役割に挑戦するために必要な力を育てます。 - 3.ミドル・シニア層の再活性化
働く意欲のある人が70歳まで活躍できる社会の実現には、50代以降の社員が停滞せず変化に適応する行動が求められます。企業もそのためのリスキリング支援を強化しています。
リスキリングの目的
- 企業にとって:「人的資源の最大化」――社員一人ひとりが持つポテンシャルを最大限に発揮すること。
- 個人にとって:「人生100年時代を生き抜くセーフティネットの確立」――性別や年齢、職歴にかかわらず、自ら成長し続けられる力を持つこと。
持続的に成長し、変化に翻弄されるのではなく適応していく。その結果、働くことを通じて社会に貢献できる存在となるのです。
5)自分自身・周囲と調和し、好循環を生み出す(行動指針その5)
キャリアとは、単に個人だけのものではなく、人と人との関係性の中で築かれるものです。一人ひとりが良いキャリアコンディションを維持することで、集団や組織全体に好循環が生まれます。
ここで参考になるのが、『ライフシフト2』で取り上げられた「社会的開拓者」という考え方です。
社会的開拓者とは、新しい社会のあり方を切り開く覚悟を持ち、自ら行動し、人生を紡いでいく人のことです。これは、社会変化に柔軟に適応しながら自在に生き抜く「プロティアン」の姿とも重なります。
社会的開拓者になるためには、組織や社会に根付いた慣習を見直し、進歩を妨げる悪習と決別し、今の時代にふさわしい働き方・生き方を体現していくことが求められます。
そのための実践ステップは次の2つです。
ステップ1:「キャリアブレーキ」を外して心豊かな状態を保つ
職場でキャリア戦略会議を開催し、不安や懸念をできるだけ書き出します。そのうえで書き出した項目を全体で共有し、解決策を共に考えていきます。このプロセスを通じて、自らキャリアを切り開くという意識に変わり、自律的キャリアへの移行が始まります。
ステップ2:心豊かな状態を新たな学びのエンジンとする
「プロティアン」の考え方を取り入れ、個人と組織の関係性をより良くするために、心豊かなチーム環境をつくり、学びを共有しながらリスキリングを実践します。この好循環により、個人の成長が他者とのつながりを通じて組織全体の力を強化することになります。
参考文献:
田中 研之輔(著)(2024)「実践するキャリアオーナーシップ:個人と組織の持続的成長を促す20の行動指針」中央経済グループパブリッシング
吉末直樹(つづく)