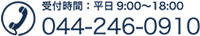ISO情報
製造業の能力開発 | ISO情報 テクノファ
ISO審査員及びISO内部監査員に経産省の白書を参考にした製造業における有用な情報をお届けします。
■製造業の能力開発
製造業における計画的なOJT を実施した事業所の割合をみると、正社員は、2008 年度からおおむね6割前後の水準で推移している。全産業と比べてやや高い水準で推移しており、製造業の正社員への計画的なOJT は、相対的に盛んに行われていることがうかがえる。直近の動きをみると、2019 年度は65.4%であったが、2020 年度は60.8%へと低下している。一方、正社員以外は、2008 年度以降20%台で推移し、全産業と比べ低い水準で推移している。直近では、2019 年度の24.1%から2020 年度の20.1%へと低下がみられる。いずれも、新型コロナウイルス感染症の発生の影響による企業の業績悪化が背景にあるものと考えられる。次に、製造業におけるOFF-JT を実施した事業所の割合をみると、正社員は、2008 年度からおおむね7割で推移し全産業とほぼ同水準となっている。直近では、2019 年度の75.7%から2020 年度の71.5%へと低下している。一方、正社員以外は、一貫して全産業より低く、2008 年度以降はおおむね30%を下回る水準で推移していたが、直近では、2019 年度の30.5%から2020 年度の21.0%まで大きく落ち込んでいる。直近の低下の動きは、計画的なOJT と同様に、いずれも、新型コロナウイルス感染症の発生の影響による企業の業績悪化が背景にあるものと考えられる。
次に、自己啓発を行った労働者の割合をみると、正社員については、2008 年度以降おおむね製造業がやや低い水準で推移しており、いずれも2008 年度から2009 年度にかけて大きく落ち込んで以降はほぼ横ばいで推移している。直近の2020 年度の製造業における自己啓発を行った正社員の割合は39.0%となっている。一方、正社員以外については、全産業より製造業がおおむね低い水準で推移しており、正社員と同様に2008 年度から2009 年度に落ち込みがみられた後はほぼ横ばいで推移している。直近の2020年度の製造業における自己啓発を行った正社員以外の割合は、15.0%となっている。
(製造業における能力開発の課題)
製造業において、能力開発や人材育成について問題があるとした事業所の割合は、近年一貫して7割を超えており、2020 年度は79.9%となっている。また、製造業は、全産業と比較しても、一貫して高くなっている。次に、製造業における能力開発や人材育成の問題点の内訳をみると、「指導する人材が不足している」(63.5%)が最も高く、次いで「人材育成を行う時間がない」(51.6%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(34.5%)、「鍛えがいのある人材が集まらない」(29.9%)の順となっている。
また、製造業における技能継承の取組内容としては、「退職者の中から必要な者を選抜して雇用延長、嘱託による再雇用を行い、指導者として活用している」(59.5%)の割合が最も高く、次いで「中途採用を増やしている」(42.2%)、「新規学卒者の採用を増やしている」(31.4%)の順となっている。製造業の現場で、人手不足、とりわけ指導する人材等の不足という課題がある中で、その対応として、退職者や中途採用者等、既に一定の能力・スキルをもつ人材の確保を進める事業所が多いことがうかがえる。
また、製造業において企業が最も重要と考える能力・スキルをみると、正社員(50 歳未満)については、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」(53.5%)の割合が最も高く、次いで「職種に特有の実践スキル」(43.7%)、「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(40.6%)、「マネジメント能力・リーダーシップ」(32.8%)、「コミュニケーション能力・説得力」(25.0%)の順となっている。また、正社員(50 歳以上)については、「マネジメント能力・リーダーシップ」(56.4%)が最も高く、次いで「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(43.0%)、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」(38.9%)、「職種に特有の実践スキル」(31.5%)の順となっている。
さらに、正社員以外については、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」(56.1%)が最も高く、次いで「職種に特有の実践スキル」(36.9%)、「定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル」(34.9%)、「コミュニケーション能力・説得力」(25.4%)の順となっている。
ものづくり人材に係るデジタル技術の活用状況について、(独)労働政策研究・研修機構(以下「JILPT」という。)の「ものづくり産業のデジタル技術活用と人材確保・育成に関する調査」(以下「JILPT調査」という。)から明らかにする。なお、JILPT 調査において、デジタル技術とは、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)やIoT(Internet of Things:モノのインターネット化)、AI(Artificial Intelligence:人工知能)周辺技術(画像・音声認識など)、RPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)など、製造現場で使われる新技術を指す。ものづくりの工程・活動におけるデジタル技術について、「活用している」とした企業は67.2%となっており、「その他(活用してない、又は該当する工程・活動がない)」とした企業(31.1%)を上回っている。
ものづくりの工程・活動においてデジタル技術を活用していると回答した企業(以下「デジタル技術活用企業」という。)におけるデジタル技術導入の効果をみると、「生産性の向上」(55.6%)の割合が最も高く、次いで「開発・リードタイムの削減」(41.5%)、「作業負担の軽減や作業効率の改善」(37.3%)、「在庫管理の効率化」(33.9%)、「高品質のものの製造」(31.4%)、「過去と同じような作業がやりやすくなる(仕事の再現率向上)」(30.0%)の順となっている。製造や開発・設計、生産管理の工程等において、約7割の企業がデジタル技術を活用する中で、生産、作業工程などにおける効率化や簡素化を実現し、製品の品質や生産性の向上につなげていることがうかがえる。
(デジタル技術を導入・活用するための課題と取組)
デジタル技術を活用していく上での課題をみると、デジタル技術活用企業とデジタル技術未活用企業(ものづくりの工程・活動においてデジタル技術を「活用していない」又は「該当する工程・活動がない」と回答した企業をいう。以下同じ。)いずれにおいても「デジタル技術導入にかかるノウハウの不足」を掲げる企業の割合が最も高く、次いで「デジタル技術の活用にあたって先導的役割を果たすことのできる人材の不足」、「デジタル技術導入にかかる予算の不足」の順となっている。
デジタル技術活用企業が、デジタル技術の活用を進めるために実施した人材育成・能力開発の取組内容をみると、「作業標準書や作業手順書の整備」(40.0%)を行った企業の割合が最も高く、次いで「OFF-JT の実施」(36.0%)、「身につけるべき知識や技能の明確化」(30.9%)の順となっている。次に、デジタル技術活用企業におけるデジタル技術の活用に向けたものづくり人材確保の取組は、「自社の既存の人材に対してデジタル技術に関連した研修・教育訓練を行う」(48.5%)の割合が最も高く、次いで「デジタル技術に精通した人材を中途採用する」(26.6%)、「デジタル技術の活用は外注するので社内で確保する必要はない」(14.0%)となっている。デジタル技術活用企業においては、外部人材の中途採用よりも、自社の既存人材の育成に力を入れていることがうかがえる。
(労働生産性の向上)
事例1
(株)内田染工場(東京都文京区)は、明治42 年創業の製品染めを専門とする老舗企業である。「顧客からの小ロット・特殊加工・至急依頼等といった難度が様々な要望に対し、迅速に対応できることが自社の強みである」と内田社長が語るように、同社は「多品種少量」製品の受注や、困難なオーダーにも即時の対応を行うことで、幅広い顧客からの受注につなげている。そのような同社の強みの根幹となる染職人の技術を支えているのは、「CCM(Computer Color Matching)」と「業務管理システム」の2つのデジタル技術である。まず、CCM の技術の導入により同社が実現したのは、作業期間の劇的な短縮と品質の平準化である。
具体的に作業が効率化したのは、本番用の色見本を作成してテスト用素材を染色するという「ビーカー染め」の工程である。この工程は、製品染めを行うに当たって重要なものであるが、以前は約2週間という作業期間を要したため、繁忙期には大量の受注に対してビーカー染めが追いつかず、注文の取りこぼし等につながる原因となっていた。また、このビーカー染めにおいては、色の調合を「職人のカン」に依存することが多く、職人によって微妙な色味の誤差が生じることがあった。こうした問題を解決すべく、色素と素材のパターンを予めCCM システムに登録し、「職人のカン」をデジタルに置き換えることで、染色品質を平準化し、作業期間を最短で1日まで短縮するなど、作業効率を飛躍的に改善することに成功したのである。このシステムの導入を主導したのは、内田社長本人だという。 同社長によれば、当初は染色工場のデジタル化に反対する社員が少なくなかったが、粘り強い説得とCCM の操作経験があった従業員の働き等により、徐々に周囲の理解も得られ、デジタル技術の全社的な活用につなげることができたという。
また、業務管理システムの導入も作業や進捗管理の効率化につながった。同システムにより、受注内容や納期及び作業状況等の一元管理が実現され、同システムに接続できるタブレットを全社員に配付することで、「いつでも・どこでも・誰でも」工場内の進捗状況を把握することが可能になった。このように積極的にデジタル技術を活用してきた同社であるが、職人の判断で丁寧に一点ずつ染色する製品もあり、デジタル技術と職人技術の共生の視点も忘れていない。同社は、「MADE IN JAPAN」の良さが改めて見直されるものづくりにおいて、デジタル技術と職人技術の両輪を回していくことで染色業界の発展に貢献していきたいと語っている。
事例2
(株)メトロール(東京都立川市)は、工場の自動化を進める上で必要となる「高精度工業用センサ」の開発から製造、販売までを一気通貫して行う企業である。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中においても過去最高の収益率を達成する同社であるが、その業績を支えているのが、デジタル技術を活用した主力製品である「着座センサ」である。
このセンサは、工作機械の治具と加工対象物の間の金属切削粉の混入等を自動で検知し、不良品の発生を防止するものである。これまでは、こうした切削粉の混入等の確認は、熟練した職人による目視など、いわゆる「職人芸」に頼らざるを得ないものであった。しかしながら、同社のセンサは、1,000 分の1ミリメートルの繰り返し精度という非常に高い精度を誇り、工作機械内部の劣悪な環境にも耐えうる設計のため、多くの工場で導入され、各工場の「職人芸」の自動化を実現し、工場全体の作業工程の効率化に貢献しているという。同社は、センサの生産管理においても、デジタル技術の活用を行っている。同社の導入する「生産管理システム」は、自社製品を製造するために必要となる約1万点にも及ぶ部品を、人の手を介さずに自動発注し、適正な在庫管理を実現するとともに、必要なときに必要な製品を供給することを可能とした。その結果、リードタイムの短縮等の作業の効率化や、製品の受注状況から製造過程における進捗状況の見える化を実現している。
デジタル技術の活用や導入に当たって大切なことは、「現場の作業を熟知した社員が参画すること」と同社の松橋社長は語る。例えば、開発システムの要件定義の際、どのような時にどういった動きが必要となるのかといった現場で働いている社員の「気づき」が重要となる。この段階から外部業者だけに任せてしまうと、社員が普段当たり前に行っている業務について対応できないなど、システムの機能が不十分で活用できない事態に陥ってしまう。デジタル技術の旗振り役は経営者が行う一方で、実際の導入から活用に当たっては、社員の参画が重要であるとし、前述の生産管理システムも、こうした社員の参画により、導入と活用を実現したという。生産管理システムの活用により省力化を実現した同社であるが、省力化により余剰となった社員の時間を、「思考」や「対話」に代表されるような「人にしかできない」創造的な業務に充てることができているという。「社員同士の役職の垣根を越えた対話」を重視する社風も相まって、更なる高付加価値な製品の製造や改良に向けて「何を自動化するか」、「どのようなことをデータ化できるか」など創造的かつ自由闊達に対話を行うことができている。このように、デジタル技術の活用が、更なる高付加価値製品の開発・製造・販売を行うための機運向上や企画立案の機会の確保に結びつき、好循環を実現している事例である。
事例3
(株)ポリコールは、樹脂製品への着色や帯電防止特性などの機能を付与させるマスターバッチを製造・販売する企業である(図1)。同社の製品は、例えば、食品パッケージ、筆記用具、自動車内装部品などに使用されており、幅広い分野・産業の顧客から需要があることが特徴である。主力工場である岩槻工場では、マスターバッチの製造に当たり、紙で印刷された製造指示書に基づき、数多くの原材料を人の手による計量、記録、配合及び検査を経て出荷していた。こうした手作業の工程により、原料の品目選定や計量のミス等が起こり、クレームにつながるケースが発生していた。とりわけ機能性マスターバッチについては、原材料の調合ミスの発見が事後の検査でも難しいことから、事前のヒューマンエラーをいかに防ぐかが課題となっていた。
そこで、同社が導入したのが、IoT 技術を用いた計量システムである。社内基幹システムと計量器をインターネットで接続し、製造指示情報が同基幹システムを通じて計量器に蓄積される。製造指示情報には「どの原材料をどれだけ使用する」等の情報が記録されており、計量の際に原材料のバーコードラベルを読み取りつつ計量器の指示どおりに作業員が計量するので、原材料の誤使用や誤計量の防止につながる。また、計量記録が自動入出力されることで計量後の何重にも及ぶ確認と記録作業が不要となり、作業工数の削減にも寄与した。その結果、従来は検査工程で品質保証の業務に従事していた社員が製造現場の業務にも従事するようになるなど、労働生産性の向上に寄与した。
同工場がこうしたシステムの導入と活用に至ったのは、現場の業務内容を熟知する社員の働きかけによるものであった。前述のクレームを受けて、長年工場において品質管理を担当し、業務内容に精通した社員と工場の製造課長が中心となり、技術研究やベンダーとの調整、現場で働く作業員への説得などを行い、社員一丸となって多くの試行錯誤を重ねることで、本格的な導入に成功した。
デジタル技術の活用による生産工程の正確性の向上、効率化を実現した同社であるが、将来的には受注や在庫管理、需要予測など他の工程におけるデジタル技術の導入を進めていきたいとしている。また、今後、デジタル技術の活用が進んでいない中小プラスチック素材製造事業者における生産工程全体のデジタル化の確立も目指すという。こうしたデジタル技術の導入に当たっては、ものづくり産業ならではの課題もある。それは、デジタル技術の専門知識を現場の社員が理解できるように噛み砕いて説明できるいわゆる「通訳」のような人材や、現場の社員が求めていることを正確に聞き取った上でデジタル技術に落とし込める「橋渡し」の役割を担う人材の不足だと工場長の島村氏は語る。また、自らの専門分野と異なる技術に対し、まずは興味をもち、情報を得ようとする社員の心持ちも重要であると指摘する。こうした人材の育成や確保を同社として図りつつも、外部の「通訳」のような人材等により、現場の社員の興味関心を喚起し、知識を高めるセミナー等があれば、ものづくり企業におけるデジタル技術の導入・活用に寄与するのではないかと同氏は語る。同社としても、こうした課題の解決を目指しつつ、今後もデジタル技術導入のモデルケースとして、更なるIoT の活用に意気込んでいる。
(出典)経済産業省 2022年版ものづくり白書
・https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2022/index.html
(つづく)Y.H