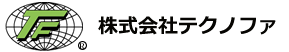044-246-0910
- 受講料
-
- 【通常価格】税込価格:35,200円 (税別 32,000円)
- 【会員価格】税込価格:31,680円 (税別 28,800円)
- 証明書等
- 修了証
- 日程
- 1日
- 筆記試験
- 無し
- 会場
- 川崎・Web
- 割引
コースの紹介
■Webセミナーにも対応■
毎年4月にコース内容を一新しているので、毎年違う内容を学ぶことができます。
※定例開催はZoomのみ。講師派遣型の場合はZoom、Teamsを選べます。
- JRCA登録 CPD研修コース(QMS/EMS)として、1コースの受講で2分野のCPD5時間30分を満たします。
このコースの特徴
【2025年度の研修内容】
≪内部監査の充実・・・停滞の壁を取り除くには≫
第1部 内部監査…よく見かける問題点と、その背景
第2部 チェックリスト事例…話し合いに焦点を当てて
第3部 内部監査プログラムの有効性を高める
第4部 力量のある内部監査員とレビュアーの充当
==講師からのメッセージ==
内部監査の充実化を特集します(第三者審査や第二者監査にも役立つ内容です)。
内部監査はマネジメントシステムのPDCAの中核をなす機能ですが、充実しなくて困っているという相談をよく受けます。また第三者認証審査では内部監査を毎回調査しますが、充実度の低い組織もよく見かけます。社内規定をオウム返ししたチェックリストを設けて、実施の有無(=適合性のみ)しか調査していない。それどころか、書類の記述と手続きのみを調査して、実態すら見ていないケースもありました。
内部監査は、マネジメントシステムの適合性と有効性の調査。有効性を調べるには、被監査者と話し合うことが重要です。今回の教材には、「話し合いに焦点を当てる」ためのチェックリスト(というよりも話題提供の切り口)の事例を含めました。
内部監査プログラム、特に内部監査チームの編成と被監査者の組合せも、内部監査の充実を図る手段となり得ます。専門性をどのように活かすか、工夫の道を探ります。
内部監査は、マネジメント力を伴うクリエイティブな業務で、適性(向き不向き)が顕著に表れます。素質ある内部監査員の候補者をスカウトすることから始まります。それ以降の育成は、内部監査の主幹者、特にレビュアーによる具体的な指摘・指導がポイントです。これらの人々の力量向上も工夫のしどころです。
これらは、審査での視点にも通じる内容で、コンサルタントの目線にもつながります。また「内部監査を審査」する際の、評価のポイントにもなり得ます。
監査・審査を“マネジメント”システムの推進に活かす道を、皆さんとともに考える。これが今回のテーマです。
カリキュラム
- 開始時間
- 10:00
- 終了時間
- 17:00
- カリキュラム
- ※毎年4月にカリキュラムが変わります。
【2025年度 カリキュラム】●内部監査・・・よく見かける問題点と、その背景 ●チェックリスト事例・・・話し合いに焦点を当てて ●内部監査プログラムの有効性を高める ●力量のある内部監査員とレビュアーの充当 ■ディスカッション ●まとめ
※●…講義 ■…演習
このコースはこんな方におすすめします。
- QMS/EMS事務局・推進担当者
- QMS/EMS審査員(補)
- コンサルタント
注意事項
- お申込みは、本ページ最下部日程の「申し込む」ボタンをクリックするとお申込みフォームに進みます。
- Webセミナー受講の方へ<Webセミナーの受講にあたり>※必ずご確認ください
コースの詳細情報
当コースをお選びいただいている理由
弊社 技術顧問を務める国府氏が、豊富な審査経験を基にISO9001、ISO14001の要求事項の解釈で間違いやすい・戸惑いやすいポイントを、審査での実例を交えた講義と、講師を交えたディスカッションを行うコースです。
有効な審査を実施・受審するための発想を得ていただきます。
受講者の声
講師紹介
国府 保周(こくぶ やすちか)
- 弊社株式会社テクノファ 技術顧問
- ISO 9001対応WG委員(ISO/TC176 国内対応委員会)
日程・空席情報
- 日程 2025年7月15日(火)
- 会場
- Web
- 日程 2025年8月29日(金)
- 会場
- 川崎
- 日程 2025年9月26日(金)
- 会場
- Web
- 日程 2025年10月20日(月)
- 会場
- Web
- 日程 2025年11月18日(火)
- 会場
- 川崎
- 日程 2025年12月12日(金)
- 会場
- Web
- 日程 2026年1月26日(月)
- 会場
- 川崎
- 日程 2026年2月10日(火)
- 会場
- Web
- 日程 2026年3月16日(月)
- 会場
- Web